リンクシェアさんの一大イベント「大見本市」では、おおよそ100社に及ぶ企業のブースが並ぶ中、別室ではセミナーや勉強会なども開催されていました。
(写真は大見本市のサントリーさんのブースの様子)


どれも参加したいセミナーばかりだったのですが、時間の都合もあり、結局、酒好きうさは「サントリーウイスキー『響12年』の楽しみ方」というリンクシェア・サロンのセミナーを受講することにしました。

実はうさはあまり「ウイスキー」を今まで飲んだことがありません。ビールやワインが好物なもので(笑)。水割りとか、かっこいいなぁとは思うけれど、味わい方というものが今ひとつわからない…というのが正直な理由でした。
ウイスキー初心者ではありましたが、このセミナーでサントリーさんのこだわりどころや、初心者でも楽しめるウイスキーの飲み方についてを教わり、その様々な魅力を知ることとなったのです♪


←写真はセミナーの様子。スライドを交えたお話のあと、各テーブルにそれぞれウイスキーを楽しめるものがセッティングされており、実際に作らせていただきました。
ウイスキーについて

ウイスキーとは蒸留酒の一つで、穀物を麦芽の酸素で糖化し、発酵させて蒸溜したものなのだそうです。
「ウイスキー」という名称は、ゲール語の「生命の水」に由来するそうですよ♪
そして、
世界の5大ウイスキーと呼ばれる中に「ジャパニーズ・ウイスキー」が誇らしげに名前を連ねているのです♪
「ジャパニーズ・ウイスキー」の特徴は、
「香味が穏やかでバランスが良く、コクもあり、水割りにも最適」なのだそうです。
文献に残っている範囲で最も古いウイスキーは1405年のアイルランドで製造されていたというもの。とはいえ、もっと昔からウイスキーは存在していたらしいそうですが、詳しいことはまだわかっていないんですって。その後は世界中に広がり、例えばクラシック音楽でいうと、ブラジルの作曲家ヴィラ=ロボスもウイスキー愛飲家の一人だったそうですよ♪
ジャパニーズ・ウイスキーを牽引してきたサントリーさんの自信作「響」シリーズ
サントリーさんは、今年(2010年)WWA(ワールド・ウイスキー・アワード)で「響21年」という21年もののウイスキーで最高賞の「ワールド・ベスト・ブレンデッドウイスキー」を獲得されたのを始め、「響17年」や「響30年」でも様々な賞を獲得しています。まさに「ジャパニーズ・ウイスキー」を牽引してきたという感じですよね♪
その「こだわり」の秘密の一部を、今回のセミナーで教えていただくことが出来ました。それは「日本人の『もの作り』に対するこだわり」に着目。昔から自然に親しんできた日本人のその繊細な技を十二分に発揮するということ!
そう言われてみると…音楽の世界でも日本人の音楽、日本の代表的作曲家・武満徹なども自然の音をこよなく愛し、「風の音」「雨の音」などを表現していますし、もっと古いところになると尺八などのいわゆる邦楽器も「自然」の音に近い音を発することの出来るものが、広まっていったわけなんですよね…。つまり…日本人の感性として、昔から自然に寄り添うことがすごく好きな人種なんじゃないのかな…と思います。お酒造りでもこの精神が生かされていると知り、思わぬところに共通項を発見しちゃいました。
ちょっと横道にそれてしまいましたが^^;
サントリーさんのこだわりはそんな「自然」と「響き合う」ウイスキーを作ることなのだそうで、水にもこだわりを持つことはもちろんのこと、この「響」シリーズのビンのデザインにも大変こだわりを持たれたそうです。

瓶が24面体になっているのです(写真がわかりづらくてごめんなさい)。
これは1日24時間、1年を24節気に区分している日本の暦を表し、長い年月をかけて作られることを表現されたのだそうです。今回の「響12年」も簡単に「12年」なんて言ってしまうけれど…考えてみるとものすごい年月ですよね…。私は12年前は一体何をしていたんだろう…ふとそんなことにも思いを馳せてみたり…。
それだけの年月寝かせるわけですから、樽の数も半端ではありません。実際にサントリーさんで持っていらっしゃる樽は100万樽を越えるそうです! そして樽の材質=何の木で作られている樽なのかによって、味が変わってくるそうですよ。

蒸溜を終えたばかりのウイスキーは無色透明なのだそうです。これらがオークの樽に詰められ、貯蔵庫で眠りにつく間に、少しずつこの琥珀色に色づいていくのだそうです。「樽」は「尊い木」。神々しい自然からの恵みを長い年月受け取っているのがウイスキーなんですね。
色と香りのハーモニー。普段何気なくいただいているウイスキーの隠された一面をかいま見た気がしました。
〈ウイスキーの楽しみ方〜響12年で興じる〉
さて、いよいよ試飲タイムです!
いただいてきたトライアルキットはこんなに贅沢にありますから♪ 楽しみが広がります。

まずはグラス選びから♪
お気に入りのグラスをとりあえず出してみて…。
やっぱり「色」も楽しみたいから、色つきのグラスはパス。
…というわけで、結局何となく「ウイスキー」の
イメージに合うようなシンプルな物をチョイスしてみました。

そして…ちょっと復習を。セミナーで教わった「響12年」のテイスティングノートのおさらいです。

セミナーでまずストレートの香りを…ということでいただいた時、うっすらとした「パイナップル」の香りを感じました。ウイスキーがこんなにフルーティーなものだったなんて知りませんでしたよ。
まずはストレートでほんのちびりといただき、次に氷を入れてオン・ザ・ロック。綺麗な琥珀色を見ているだけでほろ酔い気分(笑)。


なんか、大人の世界だわ〜(笑)。
セミナーで教わった飲み方は、もちろんストレート、ロック等を始めいくつかあったのですが、その中でもペリエ割とオレンジジュース割というカクテル風な飲み方もあり、ウイスキー初心者のうさはこちらのちょっと軽めな味がとても気に入ってしまったのでした。
さて、それじゃあ…何で割ろうかな…♪
たまたま家にあった「でこぽん」(柑橘系のフルーツ)。しかもちょっとフレッシュな「でこぽん」。このままいただいてもめっちゃ美味しいのですが、うさの矛先はもう「でこぽん」から離れなくなりました(笑)。よし! でこぽん割にしよう!


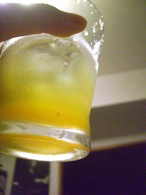
でこぽん割がどんなかって? 味はもちろん言うまでもありません! このフルーティーなテイストのウイスキーにでこぽんが合わないわけがありませんから〜(笑)。とってもハッピーな気持ちの飲み物になりましたよ☆
もう一つの楽しみ方! 雰囲気を演出してみる♪
これはウイスキーの味をアレンジするのではなく、その他のシチュエーションを演出して総合的に楽しもうという試みです♪ セミナーで教わったわけではありませんが、うさが「ウイスキー」に対するイメージを絡み合わせてみました。ウイスキーの楽しみ方番外編と言えるかもしれません。
ウイスキーのイメージってどうも「ミステリー」ものの小説がすごく合いそうな気がするのです(笑)。今回はミステリーではありませんが、今読みかけている「1Q84」のBook3もとってもウイスキーのイメージに合いそうな気がしたので、大人の雰囲気で興じてみました。
BGMは、Book3で主役の二人と同格になって登場してしまうあのちょっと気持ち悪い男性「牛河」の入浴シーン(?)にかかってくる音楽、ジャン・シベリウス(1865—1957年、フィンランドの作曲家)のヴァイオリン協奏曲をチョイス。(「牛河」の未来を暗示するかのようなこの曲についての解説は「うさうさの「around classical music」」でどうぞ。)
「響12年」を片手に小説を読み、その小説に合った音楽を聴くという楽しみ方です。こちらは、スライドショーでお楽しみくださいませ☆(BGMは著作権切れのものを使用しているのですが、表示できないので、YouTubeにてご覧ください)
…もしかして…これって総合芸術だったりしますかね? だって味覚、視覚、聴覚を十二分に味わいながら過ごせる時間だったりしますもの(笑)。
グラス越しに小説を覗くと結末まで見えてきそうな…!? そんな雰囲気のある空間を演出できる飲み物なんですね。
総じて…
ウイスキーの楽しみ方ってとても広がりがあるものだな…と実感。そして普段の生活の中でも気楽に取り入れられるのだということもわかりました^^ きっとその人に合ったそれぞれの楽しみ方があるような気がします。だから、贈り物にしてみても良いのかも…。
こんな風に、楽しみ方の例をカードに添えてみるなんてどうでしょうか?
あなたはどんな風にウイスキー「響」と興じますか?
(終売により価格高騰中—2019年追記)
12年のミニボトルは販売終了とのことです。
17年のミニボトルは山崎などとセットもので販売されています。

